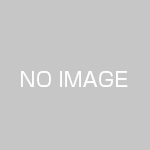おはようございます。タカハシ126(@takahashi126)です。
アラブの春に端を発したシリア危機。ロシアやアメリカはもちろん、様々な国を巻き込み、複雑な戦争になっていて6年が経とうとしているのに終わりが見えない。
終わりの始まりなんて言われてからもうどれだけ時間が経ったのか。終わりの終わりが見えない。
本の感想(レビューとまで言えない)を書くときは、なるべく書評(いわゆるレビュー)は読まないようにしている。無意識的にレビューに引っ張られる考えになると思うから。
だから、この本がどのように評価されているのか知らずに書くけど、「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」という本を何の期待もしないで読んでいた。
すると、本の端々にある言葉が時代を超えてなぜか今の僕の心に響いてきた。
故国への愛着は、故国から離れている時間と距離に比例するようであった。この距離というのは、地理的というよりも政治的、文化的意味合いの方が大きい。たとえば、亡命者の子女で、両親の故国に行ったこともない子どもほど、今現在は両親の政治的立場とは敵対する母国の自慢にひどく力が入るのである。(「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」)
内戦が続くシリア人に対して、もうシリアなんて帰らずに、ヨーロッパなどで難民としてで生活する方がマシなんではないかという人がいる。
人によってはそう思うかもしれない。でも、僕の限られた想像力で考えても、必ずしもそうではないと思う。
やっぱりみんな自分の育った、慣れ親しんだ祖国に帰りたいんだと思う。
海外での生活はかれこれ13年ほど経つ僕の場合、正直日本に帰りたいと思うことはそれほどない。それはおそらくいつでも帰れるから。帰るところは日本だという揺るぎない事実があるから。
でも、
もし、日本が帰れない国だったらどうだろう?
多分、いつか帰れる人夢見るんだと思う。
故国への愛着は、故国を離れ、帰ることのできない距離感の長さに比例するというのは一理あると思ったわけだ。
内戦が続く南米ベネズエラから来た少年ホセの言葉は、今も忘れられない。 「帰国したら、父ともども僕らは銃殺されるかもしれない。それでも帰りたい」(「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」)
こんな言葉も、多くのシリア人の胸にある気持ちかもしれない。殺されるかもしれない、悲惨な生活に戻ることになるかもしれない。それでも、帰りたい。
もちろん、そこまでして帰りたいという人ばかりではないだろう。でも、それぞれの人が拠り所としてのアイデンティティを持っているなら、故国への郷愁は誰もが持っているものではないかと感じる。
共産主義時代の東欧、そしてその後を生き抜いた体制派の人々の話を赤裸々に綴る「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」は期せずして名著と言えるほどのインパクトがあった。
匿名でのご質問などはこちらから http://ask.fm/takahashi126
タカハシ126とは:自己紹介